ENTRY NAVI
那覇の漁場
那覇近郊の漁場についてです。引用は「近代における地域漁業の形成と展開/片岡千賀之」から。
この本は九州の漁業についての本ですが、第一章が古賀辰四郎の八重山水産開発、第二章が那覇の漁業発展と鮮魚販売、第三章が沖縄県のカツオ漁業についてとなっています。引用は第二章からです。
那覇豊見城境界線で現在那覇と豊見城との間で揉めている話を取り上げましたが、那覇市が根拠としている漁業権がここで引用した漁業権(343号)です。
図は那覇市史資料編第2巻中の7、p255の図を参考にしました(正確なものではありませんので注意)。

那覇の漁業と関係する専用漁業権漁場は4ヶ所で(略)
343号は島尻郡小禄間切の地先漁場で、かつて同間切に所属していた儀間村(住吉町)も入漁権者として登録されている。
2622号は漫湖で、渡地の投網漁業者の専用漁場である。明治42年に東、西、泉崎、久茂地の漁業者11人に免許されている。那覇港の回収、埋立で昭和4年に漁業権者は上泉町の7人に変わった。
2623号は干瀬があり、那覇の優良漁場として知られるが、その管轄権は那覇・泊に授けられ、海当人が管理し、その地位は世襲されてきた。海当人は自らは漁業をせず、儀間村漁民の小魚や寄魚を対象とする網漁、糸満漁民のカゴおよびいざり漁業(サンゴ礁内の歩行漁)から入漁料をとって入漁させていた、
那覇・泊に管轄権があるといっても旧那覇に漁民はおらず、したがって実態は泊漁民の村中入会漁場であった。
4909号は慶干瀬漁場と呼ばれ、那覇港と前慶良間諸島との中間にあって船舶の避難、風待港であると同時に絶好の漁場を形成していた。明治40年に地先の渡嘉敷村漁業組合に免許された。入漁権者は垣花約40人、大峰村約80人、糸満約50人であった。
近代における地域漁業の形成と展開/片岡千賀之 p35、36(部分抜粋/省略編集)
この本は九州の漁業についての本ですが、第一章が古賀辰四郎の八重山水産開発、第二章が那覇の漁業発展と鮮魚販売、第三章が沖縄県のカツオ漁業についてとなっています。引用は第二章からです。
那覇豊見城境界線で現在那覇と豊見城との間で揉めている話を取り上げましたが、那覇市が根拠としている漁業権がここで引用した漁業権(343号)です。
図は那覇市史資料編第2巻中の7、p255の図を参考にしました(正確なものではありませんので注意)。
那覇の漁業と関係する専用漁業権漁場は4ヶ所で(略)
343号は島尻郡小禄間切の地先漁場で、かつて同間切に所属していた儀間村(住吉町)も入漁権者として登録されている。
2622号は漫湖で、渡地の投網漁業者の専用漁場である。明治42年に東、西、泉崎、久茂地の漁業者11人に免許されている。那覇港の回収、埋立で昭和4年に漁業権者は上泉町の7人に変わった。
2623号は干瀬があり、那覇の優良漁場として知られるが、その管轄権は那覇・泊に授けられ、海当人が管理し、その地位は世襲されてきた。海当人は自らは漁業をせず、儀間村漁民の小魚や寄魚を対象とする網漁、糸満漁民のカゴおよびいざり漁業(サンゴ礁内の歩行漁)から入漁料をとって入漁させていた、
那覇・泊に管轄権があるといっても旧那覇に漁民はおらず、したがって実態は泊漁民の村中入会漁場であった。
4909号は慶干瀬漁場と呼ばれ、那覇港と前慶良間諸島との中間にあって船舶の避難、風待港であると同時に絶好の漁場を形成していた。明治40年に地先の渡嘉敷村漁業組合に免許された。入漁権者は垣花約40人、大峰村約80人、糸満約50人であった。
近代における地域漁業の形成と展開/片岡千賀之 p35、36(部分抜粋/省略編集)
PR
葬儀社
大正4年の琉球新報に葬儀社開業の記事があります。
従来本県の葬儀というと肝煎人といって近隣の人や知合の人が寄り添って香花を造るやら人夫を指揮するやらして万事に不便がちであり、また繁鎖でもあることは多くの人々の経験したことであるが、其間にも時々人夫共が酒など強請って飲むやら賃銭に文句をつけて望外に得んとするなど種々てこずったものだが、此度の欠点を補ひ喪家に不便を感じせしめない目的で下泉町1の12水張小路に沖縄葬儀請負事務所なるものが出来たれば、喪家の依頼に応じて葬式一切のことを請負のださうで、一等が30円で僧侶5人に造生花4対、2等は20円で僧侶3人に造生花2対、3等は僧侶一人ださうだ。このほか墳墓を開くことだけは除いて墓口を閉することから左官の費用龕持人夫念仏に至るまですべて引き受けるそうであるから至極便利なものである。
大正4年8月21日 琉球新報(一部編集)
龕や念仏の手配までするようなので従来の形式の葬式なのでしょう。
那覇民俗地図では下泉町の松田橋そばに「ミジハイ」という文字がみえますから水張小路もその辺だったと思われます。
首里では龕は平民が担ぎ士族は不浄として触りもしないものだったらしいですが那覇ではどうだったのかは(自分は)わかりません。
参考:松田橋
従来本県の葬儀というと肝煎人といって近隣の人や知合の人が寄り添って香花を造るやら人夫を指揮するやらして万事に不便がちであり、また繁鎖でもあることは多くの人々の経験したことであるが、其間にも時々人夫共が酒など強請って飲むやら賃銭に文句をつけて望外に得んとするなど種々てこずったものだが、此度の欠点を補ひ喪家に不便を感じせしめない目的で下泉町1の12水張小路に沖縄葬儀請負事務所なるものが出来たれば、喪家の依頼に応じて葬式一切のことを請負のださうで、一等が30円で僧侶5人に造生花4対、2等は20円で僧侶3人に造生花2対、3等は僧侶一人ださうだ。このほか墳墓を開くことだけは除いて墓口を閉することから左官の費用龕持人夫念仏に至るまですべて引き受けるそうであるから至極便利なものである。
大正4年8月21日 琉球新報(一部編集)
龕や念仏の手配までするようなので従来の形式の葬式なのでしょう。
那覇民俗地図では下泉町の松田橋そばに「ミジハイ」という文字がみえますから水張小路もその辺だったと思われます。
首里では龕は平民が担ぎ士族は不浄として触りもしないものだったらしいですが那覇ではどうだったのかは(自分は)わかりません。
参考:松田橋
仏壇通り 2
仏壇通りが終焉を迎えているようです。都市計画はこんな感じ。

戦後ヤミ市に規定されてしまった那覇市のデザインの欠陥部分を更正するための計画なのがよくわかります。市街地の細い道路と周辺へ接続する道路の細さというボトルネック部分の拡大ですね。
写真は「那覇まちま~い」さまより無断借用。


惜しむ声もあるようですが町を観察していないなという感想しかもてません。大分前から仏壇屋以外は続々と移転していましたし小さな商売は安定してやっていけないような場所でした。仏壇は必要になった時にないと困るので不便な場所でも足を運ぶしかないというような性格のものですので商売としては強いです。なのでどこへいっても同じ商売です(手持ちで帰れないし)。
現在の通りは農連市場密着型バイク屋、レンタルビデオ(近所相手)、パン屋が目立つくらいでしょうか。裏手に老朽化した木造住宅が密集している場所もあるのでそこも含めて全部リニューアルということになるのでしょうね。
戦後ヤミ市に規定されてしまった那覇市のデザインの欠陥部分を更正するための計画なのがよくわかります。市街地の細い道路と周辺へ接続する道路の細さというボトルネック部分の拡大ですね。
写真は「那覇まちま~い」さまより無断借用。
惜しむ声もあるようですが町を観察していないなという感想しかもてません。大分前から仏壇屋以外は続々と移転していましたし小さな商売は安定してやっていけないような場所でした。仏壇は必要になった時にないと困るので不便な場所でも足を運ぶしかないというような性格のものですので商売としては強いです。なのでどこへいっても同じ商売です(手持ちで帰れないし)。
現在の通りは農連市場密着型バイク屋、レンタルビデオ(近所相手)、パン屋が目立つくらいでしょうか。裏手に老朽化した木造住宅が密集している場所もあるのでそこも含めて全部リニューアルということになるのでしょうね。
古波蔵村の移動
古波蔵(クファングヮ)は現在国場川沿いですが過去は裁判所付近にありました。
村は当初泉崎村・久米村久茂地の一部を含み、集落は村北西部の泉崎村などに近い小字楚辺原・真地原一帯に形成されていた。しかし1640-50年代に真和志間切から那覇町および久米村町・若狭町が町方として管轄を離れたため、村の一部(湧田村)が泉崎町の籍内となった。このため男女あわせて290人余いた村の人口は減少し、耕作のため渡名喜島より百姓を呼んだが、貢租が納めきれず身売りなどが続き、70人余までになった。こうした状況のなか、時の地頭職程順則古波蔵親雲上は1688年寄百姓制の拡充を申し出て、具志川・南風原・羽地の三間切より百姓を迎えた。しかしこの政策も功を奏さず、町方への転出が相次ぎ、また耕作地が集落から離れていたこともあって村の疲弊は続いた。1845年集落を町方から離れた場所へ移動させたいと村民からの願いがあり、国場村に隣接する小字兼久原に集落が移動した。
1880年の戸数239、人口958人
1903年の戸数254(士族127、平民127)、人口1141人(士族623、平民518)
角川辞典 p179(省略と編集)
真和志民俗地図を参考にすると楚辺原は城岳から那覇高校あたり、真地原は裁判所から王の殿あたりの一帯です。移転先の兼久原は古波蔵の原名で触れました。

疲弊した村は様々なてこ入れをおこなって復活させるのですが、功を奏さず1845年に現在地へ移転したということですね。楚辺原・真地原からは耕作地が遠かったとのことですが現在の場所近くに畑があったとしたら確かに遠いかもしれません。
那覇に編入された湧田村は旧家の屋敷と湧田サバカチと呼ばれるような平民が住んでいたようですがどんな風だったのでしょうか。
湧田には、富裕な旧家が屋根門、石垣を構えたのが多く「橋内」と誇っていたのに、それには目もくれず、湧田の先(地蔵堂の上方)に居たという、しがないサバ(草履)づくりで代表させたのが皮肉だ。
那覇人気質 2
久茂地の河原端(カーラバンタ)、譜嘉地の新村渠、湧田の先、若狭町の東より、牛マチの西側、久米村の堂小屋敷(ドウグヮーヤシキ)などは那覇の場末で細民街であった。
那覇の細民
瓦屋は城岳の東なる湧田楚辺原にあり、カラヤーと称している。焼瓦職の多きをもって名付けられ、現今那覇□□町に属する小字である。
瓦屋
与儀の地は泉崎湧田に住むものからは「ユージ・クヮングヮ」の併称で知られているだけにそれほど遠い田舎の感じは無く、また実際に毎日の生活物資の供給地でもあった。
与儀(ユージ)
村は当初泉崎村・久米村久茂地の一部を含み、集落は村北西部の泉崎村などに近い小字楚辺原・真地原一帯に形成されていた。しかし1640-50年代に真和志間切から那覇町および久米村町・若狭町が町方として管轄を離れたため、村の一部(湧田村)が泉崎町の籍内となった。このため男女あわせて290人余いた村の人口は減少し、耕作のため渡名喜島より百姓を呼んだが、貢租が納めきれず身売りなどが続き、70人余までになった。こうした状況のなか、時の地頭職程順則古波蔵親雲上は1688年寄百姓制の拡充を申し出て、具志川・南風原・羽地の三間切より百姓を迎えた。しかしこの政策も功を奏さず、町方への転出が相次ぎ、また耕作地が集落から離れていたこともあって村の疲弊は続いた。1845年集落を町方から離れた場所へ移動させたいと村民からの願いがあり、国場村に隣接する小字兼久原に集落が移動した。
1880年の戸数239、人口958人
1903年の戸数254(士族127、平民127)、人口1141人(士族623、平民518)
角川辞典 p179(省略と編集)
真和志民俗地図を参考にすると楚辺原は城岳から那覇高校あたり、真地原は裁判所から王の殿あたりの一帯です。移転先の兼久原は古波蔵の原名で触れました。
疲弊した村は様々なてこ入れをおこなって復活させるのですが、功を奏さず1845年に現在地へ移転したということですね。楚辺原・真地原からは耕作地が遠かったとのことですが現在の場所近くに畑があったとしたら確かに遠いかもしれません。
那覇に編入された湧田村は旧家の屋敷と湧田サバカチと呼ばれるような平民が住んでいたようですがどんな風だったのでしょうか。
湧田には、富裕な旧家が屋根門、石垣を構えたのが多く「橋内」と誇っていたのに、それには目もくれず、湧田の先(地蔵堂の上方)に居たという、しがないサバ(草履)づくりで代表させたのが皮肉だ。
那覇人気質 2
久茂地の河原端(カーラバンタ)、譜嘉地の新村渠、湧田の先、若狭町の東より、牛マチの西側、久米村の堂小屋敷(ドウグヮーヤシキ)などは那覇の場末で細民街であった。
那覇の細民
瓦屋は城岳の東なる湧田楚辺原にあり、カラヤーと称している。焼瓦職の多きをもって名付けられ、現今那覇□□町に属する小字である。
瓦屋
与儀の地は泉崎湧田に住むものからは「ユージ・クヮングヮ」の併称で知られているだけにそれほど遠い田舎の感じは無く、また実際に毎日の生活物資の供給地でもあった。
与儀(ユージ)
アカチラ(赤面・明津浦)
若狭町のアカチラです。図では夫婦岩のあたりに赤面原とあります。

アカチラは赤面とも明津浦とも書いてあることがあって当て字なのかと思っていましたがどちらも正しいようです。下記引用の「アカツラ」の項目で琉歌が引用されていてそれぞれの字で読まれた歌が紹介されています(歌は引用しません)。
近世の若狭町海岸砂汀地。南は潟原、西は上之毛でユーチヌサチが海に突き出していた。アカツラともみえる。
潟原から当所を通り、上之毛を巡って辻に至る道をアカチラ道と称した。アカチラの東の海中に夫婦瀬(ミートゥジー、夫婦岩とも)があった、標高5、6メートルの二つ並んだキノコ岩で潮が引けば徒歩で渡ることができた。「琉球使録」は「亀山」と記している。
アカチラからユーチヌサチ、若狭町村の北海岸一帯は那覇の女性の浜下りの場で、夫婦岩は船遊びの場であった。
角川辞典 p156(省略と編集)
「昔の那覇と私」では流れ舟として船遊びが紹介されています。
当時は伝馬船もたくさんあったのでちょっと奮発して仲間内で遊ぶよい息抜きだったのでしょうね。
流れ船というのは女性のグループが「ぬちゃーしー」で金を出し合い、伝馬を借り切って幕を張り、ごちそうをしこたま持ち込み、小鼓を乱打してはやしたて、日がな一日歌い興じて遊んだ船のこと。はたらきものと定評のある那覇女たちも三月三日は天下ご免の開放日で、結いたての髪が根元からひっくり返るほどのおおはしゃぎで唄い踊る、ほんとに「すまてのかられぬ(住み心地がよくて去り難い)」那覇の港であった。
昔の那覇と私 p63
アカチラは赤面とも明津浦とも書いてあることがあって当て字なのかと思っていましたがどちらも正しいようです。下記引用の「アカツラ」の項目で琉歌が引用されていてそれぞれの字で読まれた歌が紹介されています(歌は引用しません)。
近世の若狭町海岸砂汀地。南は潟原、西は上之毛でユーチヌサチが海に突き出していた。アカツラともみえる。
潟原から当所を通り、上之毛を巡って辻に至る道をアカチラ道と称した。アカチラの東の海中に夫婦瀬(ミートゥジー、夫婦岩とも)があった、標高5、6メートルの二つ並んだキノコ岩で潮が引けば徒歩で渡ることができた。「琉球使録」は「亀山」と記している。
アカチラからユーチヌサチ、若狭町村の北海岸一帯は那覇の女性の浜下りの場で、夫婦岩は船遊びの場であった。
角川辞典 p156(省略と編集)
「昔の那覇と私」では流れ舟として船遊びが紹介されています。
当時は伝馬船もたくさんあったのでちょっと奮発して仲間内で遊ぶよい息抜きだったのでしょうね。
流れ船というのは女性のグループが「ぬちゃーしー」で金を出し合い、伝馬を借り切って幕を張り、ごちそうをしこたま持ち込み、小鼓を乱打してはやしたて、日がな一日歌い興じて遊んだ船のこと。はたらきものと定評のある那覇女たちも三月三日は天下ご免の開放日で、結いたての髪が根元からひっくり返るほどのおおはしゃぎで唄い踊る、ほんとに「すまてのかられぬ(住み心地がよくて去り難い)」那覇の港であった。
昔の那覇と私 p63
与那覇堂村
真和志民俗地図では与那覇堂村は真和志村の範囲になっていますが明治12年に首里山川村に編入されているようです。首里民俗地図を見ると山川村との境界はすべて道になっているようなので道筋が現存するなら境界線もはっきりできるかと思います。
以下抜粋引用します。
与那覇堂村
首里城の西、首里台地の西端部に位置し、東は大鈍川村(ウドゥニガームラ)、西は真和志間切茶湯崎村(松川村)、北は真和志間切真嘉比村。真和志之平等のうち。ユナファドーと呼ぶ。
「球陽」尚貞王4(1672)年に初めて真和志郡与那覇堂村を首里府に所属させたとある。首里古地図では(略)の屋敷地のほか、北・西の真嘉比川沿いに畠・田が広がっている。畠は屋敷地の北と西に広いが、他は真嘉比川沿いにまとまっている。北西部には「鳥頭」「はるおかみ」と記された二つの丘が見える。
文化12(1815)年の士族の家部26(琉球一件帳)。
明治12(1879)年大鈍川とともに山川村に編入。
角川辞典 p113(省略と編集)
首里民俗地図は昭和初期を想定しているので大鈍川村の名前はありません。
しかし山川村の範囲内で下記引用の条件に合致する山川村の西部が大鈍川村の範囲だとおもわれます。首里の歴史本を調べればでてくるかとは思いますが当ブログの範囲外なので調べません。
大鈍川村(ウドゥニガームラ)
首里城の北西、首里台地の西斜面に立地し、北から東は山川村・真和志村、西は与那覇堂村、南は寒水川村(スンガームラ)。ウドゥニガーあるいはウドゥンガーと呼ぶ。
文化12(1815)年の士族の家部50(琉球一件帳)。
明治12(1879)年与那覇堂村とともに山川村に編入。
角川辞典 p113(省略と編集)
行政区画の変遷
真和志の区域の変遷を書いてみます(一部例外)。
那覇市域の王府時代の村々は、明治5年琉球藩、同12年沖縄県の所轄となり、
同29年小禄間切・真和志間切は島尻郡、
真和志平等・南風平等・西平等は首里区、
那覇と泊・久米・東・西・若狭町・泉崎の6村は那覇区に所属。
明治初年茶湯崎村が松川村と改称。
※明治12年山川村に大鈍川村・与那覇堂村・立岸村を合併。
明治36年真和志間切牧志村を那覇区に編入。
明治41年島嶼町村制により(略)識名・上間・仲井真・国場・安里・松川・真嘉比・与儀・古波蔵・安謝・天久の11村をもって真和志村が成立。
昭和28年市制施行して真和志市が成立。
昭和29年那覇市に首里市・小禄村を編入。
昭和32年那覇市に真和志市を編入。
※の与那覇堂村がどうだったのかがいまいちわからないんですよねぇ...昭和を想定した真和志民俗地図では松川の範囲にあるのですが。
あとWikipediaでは「1914年(大正3年) 島尻郡真和志村から壺屋地区を編入」となっていますが、そうすると明治41年の年島嶼町村制による真和志村成立時の「11村」とあわなくなってしまいます。壷屋が真和志村から那覇市へ編入というのは確かなんですが微妙にわからんとこです。
首里。
明治12上儀保村と下儀保村が合併して儀保村となる。
明治13年金城村に内金城村を合併。
明治39年首里区と西原間切の相田で境界変更が行われ、首里区石嶺・平良が起立。
明治39年首里区と南風原間切の間で境界変更。
大正10年那覇区は那覇市、首里区は首里市になる。
昭和29年那覇市に首里市・小禄村を編入。
那覇市域の王府時代の村々は、明治5年琉球藩、同12年沖縄県の所轄となり、
同29年小禄間切・真和志間切は島尻郡、
真和志平等・南風平等・西平等は首里区、
那覇と泊・久米・東・西・若狭町・泉崎の6村は那覇区に所属。
明治初年茶湯崎村が松川村と改称。
※明治12年山川村に大鈍川村・与那覇堂村・立岸村を合併。
明治36年真和志間切牧志村を那覇区に編入。
明治41年島嶼町村制により(略)識名・上間・仲井真・国場・安里・松川・真嘉比・与儀・古波蔵・安謝・天久の11村をもって真和志村が成立。
昭和28年市制施行して真和志市が成立。
昭和29年那覇市に首里市・小禄村を編入。
昭和32年那覇市に真和志市を編入。
※の与那覇堂村がどうだったのかがいまいちわからないんですよねぇ...昭和を想定した真和志民俗地図では松川の範囲にあるのですが。
あとWikipediaでは「1914年(大正3年) 島尻郡真和志村から壺屋地区を編入」となっていますが、そうすると明治41年の年島嶼町村制による真和志村成立時の「11村」とあわなくなってしまいます。壷屋が真和志村から那覇市へ編入というのは確かなんですが微妙にわからんとこです。
首里。
明治12上儀保村と下儀保村が合併して儀保村となる。
明治13年金城村に内金城村を合併。
明治39年首里区と西原間切の相田で境界変更が行われ、首里区石嶺・平良が起立。
明治39年首里区と南風原間切の間で境界変更。
大正10年那覇区は那覇市、首里区は首里市になる。
昭和29年那覇市に首里市・小禄村を編入。
松川の原名
松川の原名です。

真和志民俗地図を参考にしていますが、道や川以外の境界線は確かなものではありませんのでご注意。具体的には後原の北、与那覇堂原の川以外の境目、今帰仁原の川以外の境目、松川の西側です。
以前山川カラヤーで山川カラヤーは首里山川町とかいたのですが間違いで、山川カラヤーは与那覇堂原にもありました。
今帰仁原にはカラヤー毛というのもあります。
ちなみに読みは与那覇堂原(ユナファドーバル)、今帰仁原(ナチジンバル)です。

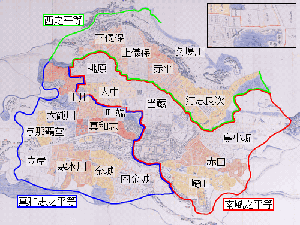
松川は観音堂から続く松川原の高台が北と南の川沿いの低地で挟まれた形になっていて変化に富んでいますね。松川原を中心として端泉社、沖縄缶詰工場、養蚕試験場、酒造所などがあります。
真和志民俗地図を参考にしていますが、道や川以外の境界線は確かなものではありませんのでご注意。具体的には後原の北、与那覇堂原の川以外の境目、今帰仁原の川以外の境目、松川の西側です。
以前山川カラヤーで山川カラヤーは首里山川町とかいたのですが間違いで、山川カラヤーは与那覇堂原にもありました。
今帰仁原にはカラヤー毛というのもあります。
ちなみに読みは与那覇堂原(ユナファドーバル)、今帰仁原(ナチジンバル)です。
松川は観音堂から続く松川原の高台が北と南の川沿いの低地で挟まれた形になっていて変化に富んでいますね。松川原を中心として端泉社、沖縄缶詰工場、養蚕試験場、酒造所などがあります。
ブログ内検索
アクセス解析
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
[08/08 なちょうらーざ]
[07/19 shimoji]
[07/19 shimoji]
[03/21 2階の店舗の娘]
[03/05 福島敏彦]
